Interview|Tamiko Nishimura/Guyu
中国のウェブメディア谷雨(qq)に写真家・西村多美子のインタビューが掲載されました。記事はこちらよりご覧いただけます (スマートフォン専用ページ)。以下、日本語版を添付いたします。

「自問自答の行程」文 ◎ 林叶
日本語校正 ◎ 石塚洋介
インタビュー協力 ◎ 羅苓寧
なぜか分からないが、西村多美子さんの写真作品を見るたびに、1967年に上映された大島渚監督の映画『日本春歌考』をいつも思い出す。映画の中で、受験のために上京した4人の若者は日本の春歌「ヨサホイ節」を歌いながら、心の中で対抗しようとしたものに対抗する。彼らは雪に足をとられながら、おぼろげにあてもなく歩いていく。彼らにとって目の前の現実は、まさにその状況のように今という時に合わず、またやり場に困る存在なのである。情欲の象徴である春歌を繰り返し歌うことしかできない彼らにとって、何に対抗するかはすでに重要ではなく、対抗すること自体がもっとも重要なのである。
西村多美子がデビュー作『実存』で撮ったのは、「状況劇場」の役者たちである。状況劇場とは、唐十郎が率いた前衛芸術の劇団で、彼らはその時代に懐疑的で、対抗的であり、その時代の市民運動や学生運動とも思想上密につながっていた。彼らの姿勢は西村多美子のカメラに、余すところなく記録された。それだけでなく、西村自身もその時代の一員として、時代の空気の薫陶を受けた抵抗者であった。学校で教えられた写真技法に従わず、35度の高温と長時間露光でプリントし、自分の感性と精神を写真の中に注いだ。まるで異なる次元において、これらの風変わりな踊り手とその時代の精神と、お互いに呼応しているようだ。この作品が撮影されたのは西村が学生であった1968年で、ちょうど「日本春歌考」が上映された翌年である。直接的な関係があるかどうか分からないが、両者にはある種共通する雰囲気がある。


1960~70年はニューレフトの運動、マイノリティの抵抗運動、現代思想が盛り上がった時代で、抵抗の文化や各種のサブカルチャーが生まれていった。当時の日本は敗戦からわずか20年しか経っておらず、積極的に戦後の再建を進めながら、その一方で、アメリカによる支配と社会全体のアメリカ化という苛酷な現実に向かわなければならなかった。経済発展と文化上の歪みが、大きな落差を生み出していった。当時、戦後の世代は、国境や人種、階級、父権、ジェンダーなどにさまざまな問いかけをし、新たな希望を探したのであった。しかしながら、このような時代の節目においては、対抗を選ぼうと、順応を選ぼうと、人々の目の前にあったのは迷いと驚きであった。このような重大な社会問題を目の当たりにして、短時間に解決方法を探すというのは容易でない。心の中で抵抗への衝動を感じつつも、見通しの悪さを感じ取り、多くの日本の写真家は偶然にして同じ旅を始めることになった。作品制作を通じて、謎解きの道を探したのだ。
2つ目の作品『しきしま』にも多かれ少なかれ同様の意味がこめられているのかもしれない。『しきしま』は大和にかかる枕詞であり、西村が作品のタイトルを考えたとき、この言葉がすぐ頭の中に現れたという。西村にとって、この言葉はまさに日本の象徴なのである。日本が全面的なアメリカナイゼーションの中にあって、あらためて日本を取り戻すこと、日本に属する伝統文化を回復することは、その時代の人たちにとって共通の問題意識であった。自分の写真集を『しきしま』としたのは、おそらくその理由だろう。彼女が探していたのは、もしかするとそのアメリカナイゼーションの元で沈み込んでいった日本だったのかもしれない。


西村が小さいころ、父親は出張先からいつも彼女にいろいろなポストカードを送ってくれたという。ポストカードの風景に西村は憧れを抱いた。卒業前に西村は沖縄へひとり旅をし、そこで日本人、白人と黒人の集まる場所が厳密に分けられいるのを目の当たりにした。ピザ屋でコーラを飲みながら、「ここは日本でない」と身をもって感じ、それは忘れられない記憶となった。卒業後、バイトや雑誌の仕事で旅費を貯め、1970年から日本全国に旅をするようになる。そして1973年、写真集『しきしま』を出版した。この作品には、荒々しい粒子、不安定な構図、ハイコントラストのイメージなど、同時代の写真表現の基調が伺える。しかし、同時代の写真家と比べると、彼女が撮った写真はぼんやりと、またうっとりとしたところが多く、逆に怒りや批判といった表現は少ない。
「写真を見返しながら、ふと「写真とは何か」と考えたりすると、無始の時より連綿と続く命の歴史と、体験したこと、意識しなかった経験、忘れてしまった記憶等、これらすべてが被写体と出会い、シャッターを切った時に、何かの形で立ち上がってくるもの……などと思った。見るものと見られるものが一体となったその先にあるものを捕らえたいと思っていた。撮った先からこぼれてしまうものを形にしたいと思った。目に見えないものを捕らえようとしているのかもしれない、と最近はうすうす感づいている。」(西村多美子、2012年)もしかすると、彼女の写真観があるからこそ、作品には暴力性が少ないのかもしれない。

元毎日新聞の写真出版部部長であった平嶋彰彦はかつて、日本の作家宫本常一のことばを引用して、西村多美子の作品をこのように解釈した。
旅をするのはなにかを発見するためである。それには歩いてものを見てみるしか方法はない。ものを見ていくと、わからないことが増えてくるが、わからないことを確かめて、明らかにするところに、旅の目的がある。
「旅にまなぶ」(「宮本常一著作集31」所載)
彼女によれば、「一人旅は自問自答の行程である。」これ以来、旅行は西村の作品制作の基本的なパターンとなった。パフォーマーを撮った「舞人木花咲耶姫」であれ、世界を回って撮った「熱い風」であれ、このような作品制作のパターンはちっとも変わらなかった。
「日本春歌考」の「若者」に歌われたように、
「君は行くのか
あてもないのに
君の行く道は 希望へと続く
空にまた 陽(ひ)がのぼるとき
若者はまた
歩きはじめる」
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
林叶 / 西村さんが学生当時の1968年ごろ、アングラ劇団「状況劇場」の写真を撮ったきっかけはなんだったのでしょうか。唐十郎や麿赤児、四谷シモンなどの怪優たちに目を見張ったそうですが、彼らは西村さんにどのような影響を与えたのでしょうか。
西村 / 写真学校の、同級生に状況劇場の役者がいて、誘われて状況劇場の公演に写真を撮りに行ったのがきっかけです。
初めての撮影だった「由比正雪」で貴重な体験をしました。
写真を始めてから1~2年目で何も分からずにシャッターを切っていたところ、藤原マキ演じる夜桜姐さんが舞台から「何も撮れやしないよ。アタシを撮る気ならアンタもこっちに越えておいで」と言った気がしたのです。ファインダーから目を離し、しばし呆然としました。藤原マキは芝居のハネた後、江戸時代の河原に立つ掘立小屋に帰って行くとしか思えない臨場感を漂わせていました。漫然とシャッターを切っても何も写らないことを夜桜姐さんに教えてもらった気がします。「結界を越えること」をこの時考えました。

林叶 /「状況劇場」で撮られた写真のほとんどに強いコントラストが見られますが、それはなぜでしょうか。写真がもっている記録性と表現性、どちらをより重視したのですか。
西村 / 学校では温度や時間を正確に現像し、きれいなネガを作ることを求められましたが、飽きたらず、実験的に高温現像や長時間露光をやっていました。舞台写真は暗い場面も多く、高温現像で像を出すように処理しました。
写真は記録であることは間違いないと思いますが、それを前提にして表現性を求めました。
林叶 /「状況劇場」を撮ったシリーズの作品は、2011年にようやく写真集「実存」として出版されましたが、どうしてこんなにも長い時間をおいて出版されたのでしょうか。
西村 /「実存」は私にとって卒業制作でした。40年近く経って、建築家で舞台美術家でもある方が、当時の写真を見たいということでご覧頂き、「面白いので本にしたらどうか」と勧められたことが写真集制作のきっかけです。また、2010年に全共闘がピークだった1968年頃を振り返る機運が高まったこともあります。
林叶 /西村さんは卒業前に沖縄へと旅行し、その後の作品制作も旅を主として撮ってこられました。なぜそのような制作方法に至ったのでしょうか。『しきしま』シリーズの制作の過程について、紹介いただけますでしょうか。
西村 / 私の幼少時に出張の多かった父が毎回、旅先から絵葉書を送ってくれ、その写真や絵に知らない世界を見て、いつか行ってみたいという憧れが、旅に出て写真を撮ることにつながっていると思います。「しきしま」の撮影時は、旅の写真をカメラ雑誌に掲載してもらい、原稿料が入るとまた旅に出るという繰り返しだった気がします。

林叶 /「しきしま」という名前には、「やまと」と「日本」という意味も含まれていますが、それにはどのような考えがあったのでしょうか。西村さんは、当時の日本をどのように理解されていたのですか。
西村 / 「しきしま」の被写体はすべて日本国内です。タイトルを考えた時、すぐに「しきしまの・・・」とやまとにかかる枕詞が浮かびました。
70年代の日本は、まだ江戸時代から明治、大正、昭和と続く風景や文化が色濃く残っていたと思います。地方はどこに行ってもその土地の個性があり、都市にまみれることなく、確たる存在感があったと思いました。
林叶 / 『しきしま』の作品においては、そのほとんどが旅行中に撮られた日常風景ですが、被写体はどう選んだのですか。作品の中に浮かんでくる日常性についてお聞かせください。
西村 / 被写体を頭で考えて選ぶことはしていません。歩きながら、または乗り物に乗りながらずっとカメラを持ち続け、インパクトがあったらすべてシャッターを切りました。普通の人の普通の暮らしの中に、ふと魅かれるものを感じたのだと思います。
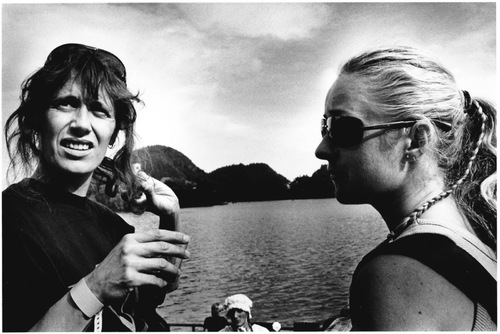

林叶 / また、これも旅行の形式で撮った作品「熱い風」ですが、これは海外旅行で撮られた作品です。どのようなきっかけで、同作品を撮られたのでしょうか。この作品の作風と、『しきしま』とはだいぶ違っています。『しきしま』には強烈な不安感がありますが、「熱い風」ではその不安感が和らぎ、実在感が強く現れてきました。まなざしは具体的なものへと注がれています。2冊の写真集の間には22年もの時間が経ちましたが、この期間に、西村さんの写真への理解には何か変化があったのでしょうか。
西村 / 「しきしま」の頃から一貫してスナップ感覚で写真を撮ってきたので、そういう意味ではスタイルは全く変わっていないです。
80年代以降の近代化で日本が均一化され、どこも似たような風景となり、旅に出る魅力が半減しました。
そこで海外に行く方向に向かいました。意識の問題だと思いますが、海外は日常性から全く切り離され、自由と孤独感が増します。そういう微妙さが写真のイメージ
を変えてみせるのかもしれません。また「しきしま」は20代前半に撮った写真で、私自身が若かったのです。
林叶 / 一番最初にカメラ雑誌に掲載された作品『猫が・・・』のシリーズでは、独特の視線で他の女性を撮られました。ご自身の説明で、「私が女であることを放棄して写真を撮ったところで、それは私にとって何のリアリティも持たないと思う」と書かれていますが、女性というアイデンティティは写真に対してどのような影響を与えたのでしょうか。また、男性写真家が撮った女性についてどう思われますか。例えば、荒木経惟や篠山紀信さんなどの作品について。
西村 / 生まれた時から女だったという事実は現実で前提にあり、写真は「私が感じたままを撮った」ということです。作品に関しては、ことさら男女の違いは考えず、むしろ個の違い、各人の個性を感じ考えました。



林叶 /『舞人木花咲耶姫』シリーズには、それまでの作品に出てきたいろいろな要素が集まっています。例えば、ダンサーや、旅行、女性など、ひとつの要素にフォーカスするわけではなく、これらのあらゆる要素を融合し、生活的な部分も入ってきています。西村さんの作品からは、ダンサーとしての木花咲耶姫だけではなく、母親として、それに普通の人としての木花咲耶姫も見受けられます。この作品にはどのような意図があったのでしょうか。
西村 / 「木花咲耶姫」はまず踊りから始まりました。肉体から出てくる表現(エネルギー)を撮りたかったのですが、目に見えない“気”のようなものを求めていたので、結局うまく捕まえられず現実に戻り、その時旅に出るという咲耶姫を引いた位置から撮ろうと決めました。旅、子供、舞を広く大きく包むように撮ることで、どういう写真になるのか、最後まで分からないのが楽しみでした。
林叶 /『舞人木花咲耶姫』と『実存』のふた作品は、同様にパフォーマーを撮られていますが、写真の表現上では大きな違いもあります。西村さんにとって、撮影対象として両者の間に何か違いがあったのでしょうか。また撮影する中で、西村さんと彼らとの関係について、どう考えられていたのですか。
西村 / パフォーマーを撮ることは好きです。肉体を通して表現されたものに興味があります。肉体そのものではなく、そこから表現されたものを撮りたいのです。1982年に「音楽」というタイトルで指揮者を撮りました。指揮棒から表現される音楽が撮りたかったのです。状況劇場の時は一体化するほど寄って撮る意識でした。木花咲耶姫は関わり方にしても引いて離れて撮ろうと思いました。撮るものと、撮られるものの位置関係は被写体によって違うものだと思います。



林叶 /森山大道さんの写真集『蜉蝣』で、協力者リスト上で、風景写真を撮った人の中に西村さんのお名前がありますね。これはどういった経緯だったのでしょうか。
西村 / 短い期間でしたが、多木浩二さんの事務所でアルバイトをしていました。多木浩二さんはプロヴォークの同人で、当時多木さんの事務所の暗室を森山大道さんや中平卓馬さんも使っていました。その時代に私の風景写真をご覧になり採用して下さったのだと思います。
林叶 / 1960〜70年代に、日本には大勢の男性写真家が出現し大きな影響を与えました。女性写真家として、そのような時代に、どのように日本の写真界での位置をつかんできたのですか。また、1990年代には、女子写真と言われるような、女性写真家の波が押し寄せ表舞台に出てきました。日本の女性写真家が伸びていくよい環境ができたようでもありましたが、日本の女性写真家の発展をどのようにご覧になっていらっしゃいますか。
西村 / もともと男性写真家、女性写真家と分けるより、一人の写真家として評価されるべきだと思っています。
しかし、60年代後半から70年代前半にかけて(この時代に私が体験したこととして)女性写真家の作品はきちんと評価されていなかったと思います。女のカメラマンがバリケードの中を撮ったとか、ヌードを撮ったとか、男性ヌードを撮ったとか、そういう捉え方で内容をきちんと見ることがなかったと思います。写真家は男であることが当たり前だったのです。90年代になって多くの女性写真家が出て来ましたが、私自身が女性写真家という意識があまりないので、当時興味はありませんでした。
女性写真家ではなく、写真家でいいのです。写真家なのです。
